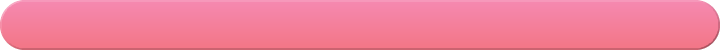- ホーム
- さかけん今日のひとこと
さかけん今日のひとこと
「ことば」って何だろう
2016/09/06
こんにちは、坂野です。
今日は「ことば」について書こうと思います。
わたしたちはふだん、自分の気持ち伝えたいときに、「ことば」を使います。
「ことば」はとても便利ですが、時折、トラブルの原因にもなります。
「そういう意味で言ったわけじゃないのに・・・」
っていうこと、ありませんか?
そうです、「行き違い」「食い違い」「誤解」です。
ありますよね。
「ことば」って便利だけど、難しいなって思いませんか?
書籍「親業」の中に、こんな一文があります。
「〜親は、子供のことば(子供の選んだ「記号」)は、単に感情を伝えるための道具でしかないことを忘れてはならない。記号はメッセージではない。親が記号を解読してやらねばならないのだ。」(「親業」p93)
この場合の「メッセージ」とは、感情、気持ちのことです。
感情はそのまま伝えられないので、伝えるために「ことば(=記号)」という道具を使います。
ところが、「ことば(=記号)」そのものはメッセージ(=気持ち)ではないので、「解読」が必要になります。
ところで・・・
・自分が本当に伝えたいメッセージ(=気持ち)にピッタリくる「ことば(=記号)」を、いつも適切に選ぶことなど、できるでしょうか?
・相手が選んだ「ことば(=記号)」を頼りに、相手が本当に伝えたいメッセージ(=気持ち)を、いつも正確に解読することなど、できるでしょうか?
「行き違い」「食い違い」「誤解」の原因は、そこにあります。
そして、「心が通いあう」コミュニケーションを図るヒントも、実はそこにあるのです。
人は、他者との関係の中で生きています。
「心のふれあい」を感じながら、生きていきたいものですね。
今日は、「ことば」について書いてみました。
必要な方に届きますように。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<お知らせ>
「親業訓練一般講座」受講生の募集を開始しました!
この講座では、①相手の気持ちを理解する聞き方、②自分の気持ちを上手に伝える話し方、③欲求や価値観が対立したときの解消の仕方、を学びます。
ご予約ページに、講座について詳しく書かれています。
ぜひチェックしてくださいね!!
↓↓↓
なぜ「そのままでいい」のか
2016/05/23
こんにちは、坂野です。
今日は「そのままでいい」ということについて書こうと思います。
たとえば子どもが学校のテストで100点を取って帰ってきたとします。
親としては、嬉しくまた誇らしく思って、たくさん褒めるかもしれません。
一方また別の日に、今度は0点の答案用紙を持って帰ってきたとします。
びっくりして、ガッカリして、つい叱ってしまうかもしれません。
前者の場合に「そのままでいい」と言い、後者のときは「そのままではよくない」と伝えるなら、これはもしかすると「親の評価」を伝えていることになるかもしれません。
もし「親の評価」を伝えたいのなら、それでいいかもしれません。
ところで、子どもがどんな状態であっても、「そのままでいい」と言うのはいかがでしょうか?
「何でもいいわけはないでしょう」と言われるかもしれません。
確かにそうかもしれません。
ただ、子どもには、どんなときでも「そのままでいい」というものがあると思います。
それは、存在価値です。
そもそも、存在にいいも悪いもありません。存在は、評価したり比較したりできないからです。
子どもたちには、できるだけたくさん「そのままでいい」と伝えたいものです。
これは、行為と存在を切り離して初めてできることかもしれません。
子どもに親の「評価」ではなく、「そのままでいい」という親の気持ち(=受容)が伝わって初めて、親の愛が伝わったことになるのではないかと思います。
今日は「そのままでいい」ということについて書いてみました。
必要な人に届いたら嬉しいです。
違うこと、劣っていること
2016/05/18
こんにちは、坂野です。
生まれながらの脳のタイプによって、コミュニケーションの取り方が大多数の子どもたちと異なっていたり、見え方、記憶の仕方、理解の仕方などにも違いが見られたりする子どもたちがいます。
親としては、自分の子どもが他の子と違っていると不安になってしまいますね。
子どもたち自身も、他の子に難なくできることが自分にはできないと、自信をなくして自分のことが嫌いになったりするかもしれません。
ところで、「違う」ということは「劣っている」ということでしょうか。
よく考えてみると、違っていることと、劣っていることには、何ら関係がないということに気が付くかもしれません。
ここが自分の中でうまく整理できると、たとえ我が子が大多数の子どもと違っていても、その違いをしっかり受け止められるかもしれません。
そして、その違いがもつ素晴らしさにも目を向ける余裕が生まれるかもしれません。
今日は、違っていることと、劣っていることについて書いてみました。
必要な人に届いたら嬉しいです。
気持ちを聞くこと〜アスペルガーのAちゃんの話〜
2016/04/20
こんにちは、坂野です。
発達障害をもつお子さんと接する機会が多いのですが、先日こんなことがありました。
その子(Aちゃんとします)は、広汎性発達障害と診断されていて、特にアスペルガー傾向が強く見られるお子さんです。
その日Aちゃんは、「人の気持ちが分からないなんてばかじゃんか!!」と大声を上げて泣きました。
これはAちゃんがある大人に対して言った言葉でした。
アスペルガー症候群の人は脳機能にかたよりがあり、その影響で社会性や想像力、コミュニケーションなどに独特のくせが見られます。
(心の病気と誤解されることがありますが、心や体に異常があるわけではありません)
Aちゃんは他者とのコミュニケーションに難しさを抱えていて、本人はとても苦労しています。
本人のその生きづらさを少しでも軽減していくことが、本人とまわりの大人に求められることだと思います。
でも問題を抱えているのは本人だけでしょうか。
学ぶ必要があるのは本人だけでしょうか。
アスペルガー症候群は一般に「察することの障害」といわれています。
でもAちゃんの言葉から読み取れるように、本人は自分の気持ちが理解されることを欲しています。
もちろん、本人には自分の気持ちを伝える方法を、少しずつ身に付けていって欲しいと願っています。
でもまわりの大人が、子どもの気持ちを聞く方法、理解する方法を学ぶことも同じく大切だと思っています。
そのひとつとして、「聞き方を伝える」ということを、これからも続けていきたいと思っています。
開かれた心を開けたままにしておくために
2016/04/08
こんにちは、坂野です。
前回の記事で心の扉を開く「ことば」について書きました。
今日は、開かれた心を開けたままにしておくための、親(聞き手)側の聞き方について書きたいと思います。
一般に「聞く」というと、受信者側なので、受け身の印象が強いかもしれません。
今日ご紹介したいのは、沈黙・寡黙・相づちといった「受動的な聞き方」ではなく、その逆の「能動的(あるいは活動的)な聞き方」です。
この聞き方は、開かれた心を開けたままにしておくためにとても効果的な聞き方です。
たとえば子どもが、
「今日は学校に行きたくないな」
と言った場合、次のように応じるのが能動的な聞き方と言うことができます。
「今日は学校に行きたくないんだね」(くり返し)
「今日は学校を休みたいんだね」(言い換え)
「今日は気が進まないんだね」(気持ちをくむ)
このような応じ方をすると子どもは、自分の投げた球を受け止めてもらえたと感じやすくなります。
そしてさらに続きを話そうという気持ちになりやすくなると思います。
良かったら試してみてくださいね。
どなたかのお役に立ちましたら嬉しいです。
【ご案内】
「カウンセリング基礎講座〜上手な聞き方のコツ〜」のお申込み受付中!!!
詳細はコチラ↓↓↓
是非お早めにお申込みくださいませ。
皆様のお越しをお待ちしております。
関連エントリー
-
 夫婦・カップルカウンセリングの内容と流れ
お一人でお越しの場合 所要時間は約2時間です。 事前準備は必要ありませんので、リラックスしてお越しください
夫婦・カップルカウンセリングの内容と流れ
お一人でお越しの場合 所要時間は約2時間です。 事前準備は必要ありませんので、リラックスしてお越しください
-
 おススメ図書のコーナーを更新しました
おススメ図書のコーナーに「夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本」(宮尾 益知 (著), 滝口 のぞみ (監修
おススメ図書のコーナーを更新しました
おススメ図書のコーナーに「夫がアスペルガーと思ったとき妻が読む本」(宮尾 益知 (著), 滝口 のぞみ (監修
-
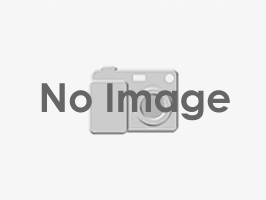 ルーム案内のページを更新しました
ルーム案内のページを更新しました。https://www.c-r-smile.com/contents_4.h
ルーム案内のページを更新しました
ルーム案内のページを更新しました。https://www.c-r-smile.com/contents_4.h
-
 おススメ図書のコーナーを更新しました
おススメ図書のコーナーに「がんばることをやめられない コントロールできない感情と「トラウマ」の関係 (鈴木 裕
おススメ図書のコーナーを更新しました
おススメ図書のコーナーに「がんばることをやめられない コントロールできない感情と「トラウマ」の関係 (鈴木 裕
-
 おススメ図書のコーナーを更新しました
おススメ図書のコーナーに「カルトからの脱会と回復のための手引き《改訂版》――〈必ず光が見えてくる〉本人・家族・
おススメ図書のコーナーを更新しました
おススメ図書のコーナーに「カルトからの脱会と回復のための手引き《改訂版》――〈必ず光が見えてくる〉本人・家族・
カウンセリングルームスマイル
親業(おやぎょう)ほっとスマイル
オンラインスクールスマイル
お気軽にお電話ください。LINEもお気軽にどうぞ。
ご連絡をお待ちしています。
電話番号:086-238-6117(受付時間8:30〜23:00)
所在地 :岡山県岡山市南区立川町3-26
営業時間:10:00〜22:00
定休日:不定休

LINE登録はお気軽にどうぞ↓

【参考:スマホの画面上のQRコードを読み取る方法】
①画面に表示されるQRコードを長押しして、端末に保存。
②LINEアプリを開き、ホーム→友だち追加→QRコード→①で保存した画像を選ぶ。
※端末によってはこの方法では登録できない場合があります。